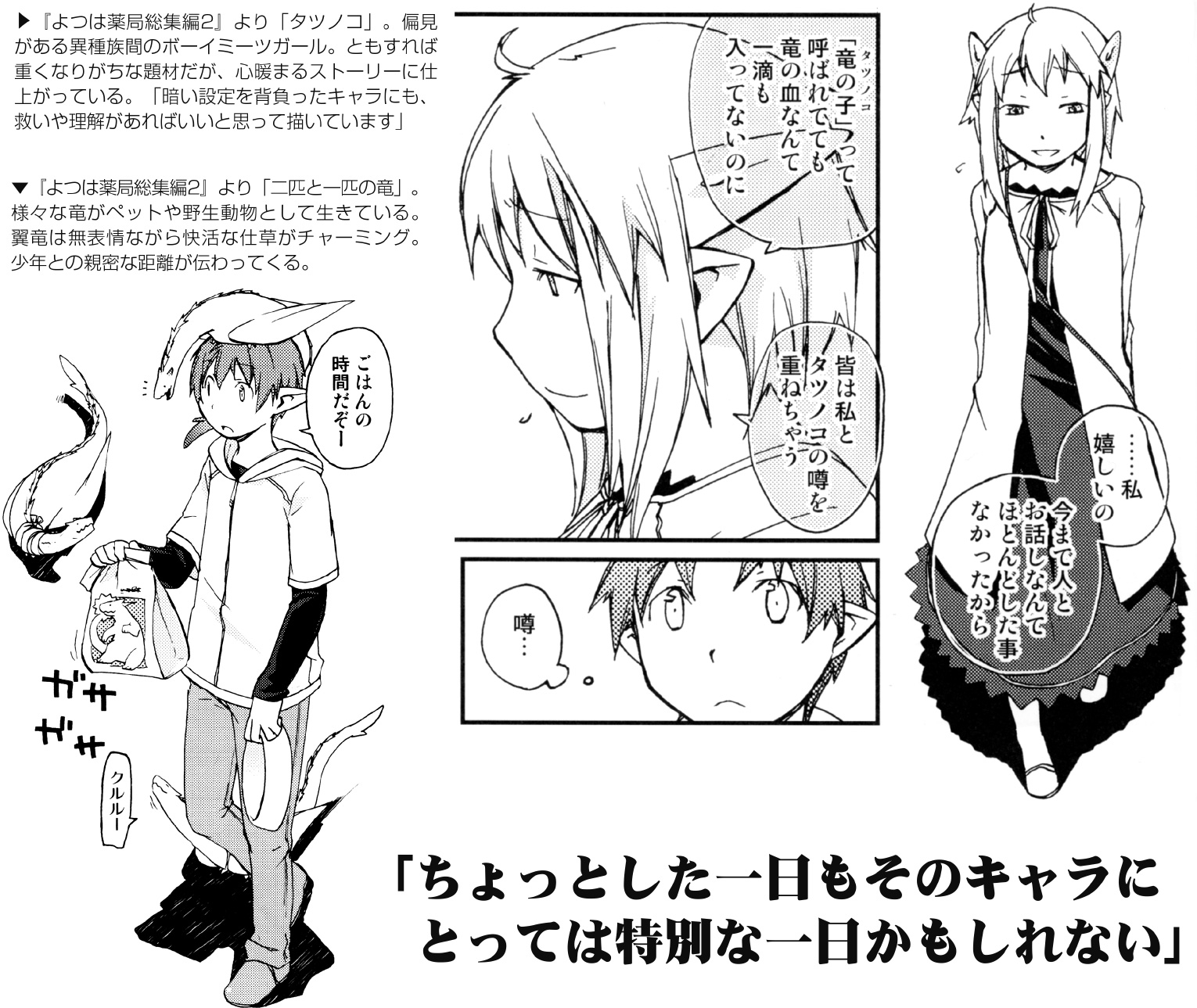鷹行静つらんとんてん玉子に目鼻

- 生年月日…12月23日
- 職業…図書館司書
- 趣味…漫画、料理、旅行
- コミティア歴…コミティア104から
- https://pixiv.me/siztakayuki

他に類を見ない珍しいサークル名は、百人一首所収の文屋朝康の歌の下の句を覚えるために祖父から教わった語呂合わせと、「玉のようにキラリと光るものを目指したい」との気持ちを掛け合わせたもの。
高校、大学と学生時代は演劇少女だったという鷹行静さん。読者として漫画には親しんでいたものの、社会人になってから自身で執筆を始めたのは、十代の頃に『ポーの一族』を読んで特に感銘を受けたことと、就職活動で行き詰まっていた時のあるひらめきがきっかけだった。「演劇ではできなかったことが、漫画でならできるかもって思ったんです」
就職後、舞台用だったシナリオを元に、試行錯誤を繰り返しながら初めて完成させた読切「帰る」で、10年に『月刊アフタヌーン』の四季賞準入選を受賞。本格的にプロを目指すために退職し、アシスタントをしながら漫画修業を続けたが、読切が一本掲載されて以降、努力が実を結ばず活動を一時断念。そんな時に、作品発表の場を求めてコミティアへの参加を決めた。「『このままでは漫画を描かなくなってしまう』という危機感がありましたし、家で眠っていた商業誌の没ネームをきちんと形にして、人に読んでもらうことで供養したかったんです」。同人誌では、地下鉄構内に店を構える沖縄物産展で働く女性と、その周囲を行き交う人々の群像劇『地下鉄に花と花唄』や、ベテランOLのベールに包まれた半生を後輩の新人の視線で描く『児玉さん』など、“普通の大人たち”が、日常の中で人生について深く想いを巡らせるドラマを発表し続けている。
コミティア120発行の『帰る』は四季賞受賞作で、東京で働く主人公・加代が夜行バスで新潟の実家に帰省するまでを描いた物語。旅の途中途中で、彼女自身や家族、同僚、偶然居合わせた他人など、取り巻く人々の人生のワンシーンが走馬燈のように浮かび上がっては消えていく。「日常の中で主人公の気持ちが動く瞬間を追体験できる作品が目標」と語る鷹行さん。実家から足が遠のいていた加代の今現在の状況や、何を思い急な帰省を決めたのかを読み解く面白さがある作品だ。
今の第一目標は、コンスタントに作品を完成させ発表を続けること。「ふと立ち止まってしまった人がもう一度歩き出して、物語から出てゆく後姿を描き続けたいです」。もがき悩んだ時期を抜け出し、表現者として新たな道へと歩み出しつつある鷹行さんが、そのペンで今後、人生の第二幕をどのように切り拓いていくのか、観客席からじっくり見守りたい。
高校、大学と学生時代は演劇少女だったという鷹行静さん。読者として漫画には親しんでいたものの、社会人になってから自身で執筆を始めたのは、十代の頃に『ポーの一族』を読んで特に感銘を受けたことと、就職活動で行き詰まっていた時のあるひらめきがきっかけだった。「演劇ではできなかったことが、漫画でならできるかもって思ったんです」
就職後、舞台用だったシナリオを元に、試行錯誤を繰り返しながら初めて完成させた読切「帰る」で、10年に『月刊アフタヌーン』の四季賞準入選を受賞。本格的にプロを目指すために退職し、アシスタントをしながら漫画修業を続けたが、読切が一本掲載されて以降、努力が実を結ばず活動を一時断念。そんな時に、作品発表の場を求めてコミティアへの参加を決めた。「『このままでは漫画を描かなくなってしまう』という危機感がありましたし、家で眠っていた商業誌の没ネームをきちんと形にして、人に読んでもらうことで供養したかったんです」。同人誌では、地下鉄構内に店を構える沖縄物産展で働く女性と、その周囲を行き交う人々の群像劇『地下鉄に花と花唄』や、ベテランOLのベールに包まれた半生を後輩の新人の視線で描く『児玉さん』など、“普通の大人たち”が、日常の中で人生について深く想いを巡らせるドラマを発表し続けている。
コミティア120発行の『帰る』は四季賞受賞作で、東京で働く主人公・加代が夜行バスで新潟の実家に帰省するまでを描いた物語。旅の途中途中で、彼女自身や家族、同僚、偶然居合わせた他人など、取り巻く人々の人生のワンシーンが走馬燈のように浮かび上がっては消えていく。「日常の中で主人公の気持ちが動く瞬間を追体験できる作品が目標」と語る鷹行さん。実家から足が遠のいていた加代の今現在の状況や、何を思い急な帰省を決めたのかを読み解く面白さがある作品だ。
今の第一目標は、コンスタントに作品を完成させ発表を続けること。「ふと立ち止まってしまった人がもう一度歩き出して、物語から出てゆく後姿を描き続けたいです」。もがき悩んだ時期を抜け出し、表現者として新たな道へと歩み出しつつある鷹行さんが、そのペンで今後、人生の第二幕をどのように切り拓いていくのか、観客席からじっくり見守りたい。
TEXT /KENJI NAKAYAMA ティアズマガジン122に収録